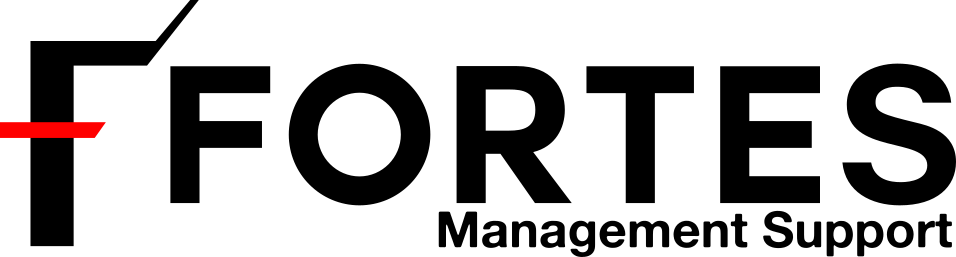これまでのキャリアのこと(1)
0.はじめに
2024年3月に、1998年7月から25年9カ月続けてきた地方公務員としてのキャリアを卒業しました。
北海道と旭川市という二つの自治体を、研究職員と事務職員という二つの職で歩いてきたことになりますが、いずれの職場にも大変お世話になり、今の自分の基盤を築いてくださった諸先輩や同僚の皆さんには感謝するばかりです。
2024年4月からは、中小企業診断士と行政書士としての個人事務所を運営しつつ生計を立てています。
行政書士資格は行政事務経験者であることによる、いわゆる6号特認での開業です。中小企業診断士は、市役所に勤務していた2009年に試験合格し、2010年に登録をしました。
ここでは、それ等を含めて現在までのことを振り返りつつ、後輩に何か伝えられることがあれば、もしくは、これから地方公務員や地方独立行政法人職員を目指す方の参考になればと思い、何回かにわたり短い文章を書いていこうと思います。
思い出話ともエッセイともつかない内容になるかとは思いますが、どうかお付き合いいただけますでしょうか。
今回は、どうして自治体を就職先として選んだのかということについて書きたいと思います。
大学で私は、農学部で林業と木材について教える森林科学科に所属していました。
卒業研究では樹木の生長について調査し、大学院でも引き続き、その辺に生えている樹からサンプルを採取してきて、観察試料を作成し、顕微鏡を覗き記録をつけるという毎日を過ごしていました。
この学科の学生が就職する先は、紙パルプ、木材木製品、建設会社、林業会社など、木に関係する事業だけでなく、商社や広告代理店、IT関係までと多岐にわたるのが特徴です。なかでも、国家・地方を問わず、林業関係の技術系公務員は、毎年一定の合格・採用者がある、いわば主流ともいえる進路です。
私は北海道内に研究職として就職することを希望していましたので、第一志望の就職先は、北海道庁の出先機関である林産試験場でありました。
大学院修士課程2年目のある日、教授に呼ばれて出向いて行ったところ、林産試験場で選考による採用試験があるから受けてみないか、ただし受験者は複数名いるらしい、との話を賜りました。第一志望の先ですし、特に断る理由もありません。また、仮に不合格になっても、そのまま在学しながら次の定期採用試験を受けることができるタイミングでしたから、自分にとって何の不利益もありません。その場で、受けますと返事をした記憶があります。
その少し後に筆記と面接の試験を受け、合格の知らせが届き、7月採用者として旭川へ赴任せよとの指示がありました。教授にはこのとき、大学院に籍を残して二足の草鞋を履かせてほしいと頼んだのですが、あえなく断られました。ですので修士課程は中退です。
まあ、そのような経緯で、北海道庁の職員となることができました。自分が生まれ育った、大好きな北海道のために仕事ができると誇らしく思ったものです。とはいえ正直なところは、家からスキー場まで、車で15分程度で行くことができるのが何よりうれしかったです。